
美しい家をつくろう~層の家プロジェクト後編~
建築家・三原宏文×森田健司
美しい器に住むことで、暮らしの時間が豊かになるのだと思う。住まいの器が美しいと自然に暮らし方も美しくなるような気がする。今までにない物の見方や感性が生まれてくると、楽しい暮らしのバリエーションが増えてくるものだ。ちょっとした暮らしのシーンだからこだわって過ごしたいと思う。

アーキテクトな感性を暮らしの中のシーンに取り入れてゆく。
その感性は建築デザインやインテリア、家族にとって心地よい時間などあらゆるものに取り入れられ、
家族にとって唯一無二の心地よさが生まれる。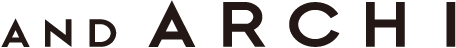
河合工務店の新しいモデルハウスが愛知県一宮市に竣工した。設計者は、東京に椙(すぎ)設計室を主催する稲沢謙吾氏。
河合工務店の施工力だからこそ挑戦できる設計を目指した。河合社長と建築家稲沢氏の答えは、木の本来持つ質感をそのまま生かした設計計画。難しい「設計」「施工」に敢えて挑むモデルハウス建築となった。
Feature|July.2024

美しい器に住むことで、暮らしの時間が豊かになるのだと思う。住まいの器が美しいと自然に暮らし方も美しくなるような気がする。今までにない物の見方や感性が生まれてくると、楽しい暮らしのバリエーションが増えてくるものだ。ちょっとした暮らしのシーンだからこだわって過ごしたいと思う。


美しいという要素は、住宅にとって大切な性能の一つだと思う。人はモノを大切にする時、いつまでも飽きのこないデザインと住んでいて楽しいという品質を求めるのだと思う。建築物のみならず、名車と呼ばれるものや美術品に至るまで様々なものがデザインと共に残されてきた。美しいものは残すに値するものなのだから。


N9デザインが挑戦したモデルハウスは、「設計」と「性能」と「技術」の関係性の中でつくられている。G3の住まいづくりは、これらの要素の何が欠けても成り立たない。ただ、性能の良い住宅をつくるということにとどまらないブランドがN9デザインだ。


中澤勝一建築のN9designモデルハウスが、どのようなコンセプトで作り上げられてきたのかを解剖する。N9designがHEAT20 G3のスペックの住宅性能を採用した理由は、「豊かな暮らし」を提供するための手段である。性能×設計×技術から生み出される住まいの価値を体感できるモデルハウスとなった。


MORIKEN HAUSの森田氏のモデルハウス計画は「畑の横の土地」を選んだ。森田氏は敷地の特性を活かしたモデルハウスの設計を求め、建築家河添氏は畑の隣という環境を建築家の感性で捉えにいく。


狭小地で隣家が迫る敷地条件で、モデルハウスの設計プロジェクトが始まった。設計力という魅力を伝えたい森田氏の狙いを込めたモデルハウス計画。建築家・戸高氏はこの狭小という敷地条件の中に可能性を見い出していく。


アンドマイスター。マイスターはドイツ語で「巨匠」とか「職人」という意味を持つ。and archiでは、設計者とのプランニングから建築現場の職人の仕事や家具などのプロダクトに至るまで「ものづくり」の魅力に焦点を当てていく。


7年前に建築されたクレイルのモデルハウス。色あせないモデルハウスの設計は、建築家矢橋徹の感性から生み出された。感性は最も説明のしづらい言葉だ。矢橋氏は、その「感性」を形にし、その感性を言葉として「言語化」していく。


リビングの定義は何か?家族の団らんの場、一般的にはソファーやテレビを置いて寛ぐ空間のことを言うのだろう。しかし、建築家・飯塚氏の設計にはそのような定義は無いのかもしれない。住宅という限られた大きさの中に最大限の寛ぎをインストールする。その居場所の可能性を、飯塚氏とゼルコバデザインの日高氏は考察する。


ここは愛知県東海市の閑静な住宅街。河合工務店の小林氏の自邸を建てるプロジェクト。もともと祖母が所有していた畑を利用し住宅計画が始まった。設計者は田辺真明建築設計事務所の田辺氏に白羽の矢が立った。祖母の畑だった土地の面影を新たなプロジェクトの中にもコンセプトとして残したいと考えた。


今回のプロジェクトの設計者はn+archistudioの中村文典氏。中村氏は福岡で設計事務所を構え、福岡のみならず全国で数多くの設計に従事している。バイクや車、キャンプなど数多くの趣味を持ち、あらゆる感性にアンテナを伸ばしながら幅広い見識を武器に設計をしている。


売り主と買い主の利益をそれぞれ最大化するためにエージェントは存在する。不動産取引は様々な形態がある。注文建築のための土地の売買や資産運用の為の投資物件、不動産相続の相談などエージェントのシゴトは多岐にわたる。それぞれの専門性を持ち顧客のニーズに応えていくのが一流のエージェント。そんなエージェントのシゴトを&Haus Agentが紐解いていく。


田島氏はクレイルの施工性能を熟知した上で設計をしている。性能があるからこそ成り立つ空間設計がある。設計者と施工者の相互の理解が暮らしの楽しみの可能性を広げていく。


「家づくりは最高に面白い!」そんな想いを伝えたいとスタートした家づくりの奥深さ、楽しさを知る者たちによるクロスオーバートーク。第3回は、土地を深く読み解き、建物のあるべき姿を追求する。


「家づくりは最高に面白い!」そんな想いを伝えたいとスタートした家づくりの奥深さ、楽しさを知る者たちによるクロスオーバートーク第2弾。既成概念を突破するという視点が空間の可能性を広げていく。


玄関ポーチと2階の窓の開口部(フレーム)が印象的な「静岡葵モデルハウス」。この印象的な建物のデザインには理由がある。住宅工房コイズミの小泉氏は、あえて条件の厳しい立地にモデルハウスを建てることを選択した。敷地条件の厳しさが建築家の設計力を引き出しやすいと考えたからだ。


シャープなフォルム、ベージュグレーの外壁に白いサッシの大きな窓。広島県のO邸は、やさしい色合いや素材感の中にも芯の強さと普遍性をたたえた外観が印象的な家だ。どのようにしてこの家は建てられたのか。建築家であるアーキテクチャー・ラボ石川昂建築設計事務所の石川昂氏、工務店CODA DESIGNの小林大輔氏、施主であるO夫妻に話を聞いた。

家づくりの奥深さ、楽しさを知る者たちによるクロスオーバートーク。最終回のトークテーマは「新しい暮らしの快適性。それを生み出すポイント」心地よい暮らしに隠されたヒミツとは何か? 家づくりの本質に迫ってみた。


家づくりの奥深さ、楽しさを知る者たちによるクロスオーバートーク。第3回目のテーマは、「はじめての家づくりに不安を感じる人のための処方箋」。はじめての家づくりにつきまとう不安や疑問の解消方法などについて語り合ってもらった。


「家づくりは最高に面白い!」そんな想いを伝えたいとスタートした、家づくりの奥深さ、楽しさを知る者たちによるクロスオーバートーク。第2回目は「間違いのない土地探し、建築会社選びを行う方程式」と題し、ベストな選択をするためのノウハウについて熱く語り合ってもらった。


「家づくりは最高に面白い!」家づくりを数多く手がけた立場、数多の施主の声を聞いてきた者たちによるクロスオーバートーク。いま求められている家づくりや、家づくりの魅力、楽しさとは何かを紐解いていく。
