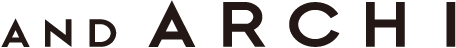藤本誠生建築設計事務所が監理・設計する建築が福岡県福岡市で完成した。施工はフィルハウスデザイン(株式会社イーコムハウジング)が担当した。建築面積の大きさからは想像もつかない広がり感のある住まいができあがった。施主と建築家の相互の理解から生み出された住宅は、敷地に対して素直でシンプルなものだった。
[ 監理・設計:藤本誠生建築設計事務所 藤本誠生 施工:フィルハウスデザイン 所在地:福岡県福岡市 ]
- 敷地面積:132.28m2 (40.01 坪)
- 延床面積:86.38m2 (26.12 坪)
- 耐震等級3 | C値:0.14cm2 / m2 | Ua値:0.33w / m2・K
デザインとは問題解決なのだと思う【後編】
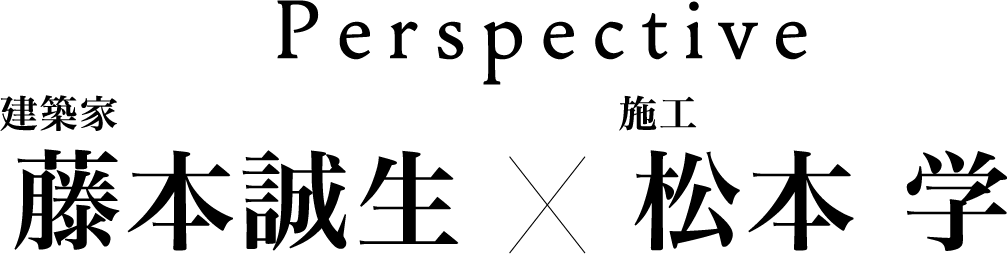 Feature|Jan.2025
Feature|Jan.2025




自然に寄り添う住宅設計の手法
藤本誠生建築設計事務所が手がける住宅設計は、「自然さ」を意識して今回のプロジェクトに取り組んだ。この「自然さ」とは、敷地の形状、建築素材の特性、そして住む人々の生活スタイルに正面から向き合い、最適な設計を導き出すということ。これにより生まれる住宅は、住まい手にとっての本質的な快適性を実現し、日常に調和した空間を提供する。
特に、南道路に面した敷地条件においては、一般的な「南向きの大きな窓」をあえて設けない設計手法を採用することで、道路からの視線や夏場の直射日光による室内環境の悪化といった問題を解消している。この大胆な選択が、光と風を最大限に取り入れ、住まい手のプライバシーを確保しながらも居住空間の質を向上させる結果を生んでいる。


敷地を読み解くことから始まる設計
藤本氏の設計に対する向き合い方は敷地を単なる土地として捉えるのではなく、その場が持つ「特性」や「声」に耳を傾けることが重要とされている。風の流れ、日照条件、隣地の影響、周辺環境との関係性を徹底的に分析し、それを設計に反映することによって、その敷地ならではの可能性を引き出す。
例えば、斜面地においては階段状の設計を採用し、地形と調和する住宅を実現する。また、狭小地ではスキップフロアや中庭を活用して空間の広がりを確保し、視覚的な広がりと実用性を両立させています。こうしたアプローチは、敷地の制約を設計の価値へと変換する具体例といえる。
今回のプロジェクジェクトにおいては、道路が南に面する建築条件の良い敷地条件だが南に大きな窓などの開口部を設けると明るく開放性のある建築ができる反面、プライバシーの阻害を受けるという状況だった。周りの目を気にすることなくアウトドアリビングを愉しく快適に過ごすための空間構成を確保することがミッションとなった。


東西方向の窓が生み出す空間の可能性
藤本氏の今回の住宅設計では、南向き窓の代わりに東西方向に開かれた窓を採用することが特徴。この設計により、朝の柔らかな光を東から入ると共に中庭の内壁からの反射光も取り入れる。そして午後からの温かい光を西から取り込み、夕方以降の西日は程よく中庭の壁が遮ってくれる。一日を通じて変化する自然光が室内空間を豊かに彩り、居住者に時間の移ろいを感じさせる効果をもたらすのだ。
また、窓間に柱や梁を表しとして見せるデザインが取り入れられている。これにより、構造体そのものが空間のリズムと一体感を形成し、素材の質感を視覚的にも触覚的にも味わうことができる。光がこれらの構造体に影を落とし、陰影の変化が空間に動的な表情を加えてくれるのも藤本設計の醍醐味である。


中庭がもたらす居住環境の向上
西側には中庭が設けられ、内と外をつなぐ重要な空間として機能しています。この中庭は単なる景観要素ではなく、プライバシーの確保と開放感の両立を実現するデザインとして位置づけられている。さらに、中庭の壁は夏場の強い西日を遮り、室温の上昇を防ぐ役割を果たします。
植栽を施した中庭は、風に揺れる葉の影や四季折々の変化を室内にもたらし、住まい手が自然とのつながりを感じられる場となります。この空間設計により、住まいの内と外が視覚的に一体化し、居住空間の広がりが生まれています。


素材が語る自然との共生
素材の選択は、藤本氏の設計において欠かせない要素だ。柱や梁をそのまま見せる手法は、木材の持つ温もりや力強さを引き立てるだけでなく、住まい全体にリズム感を与えている。これらの自然素材は経年変化を楽しむことができ、時間が経つほどに住まい手との愛着を深める要素となる。
地元産の木材や手仕事による仕上げ材を積極的に採用することで、その土地ならではの特徴を住宅に反映させることが可能となる。これにより、住宅がその地域の文化や風土と調和した存在となり、住む人々にとって特別な意味を持つ空間が形作られるのだ。
住まい手の生活を中心にした設計
藤本氏の設計では、住まい手の暮らし方や価値観が常に設計の中心に据える。家族構成や趣味、将来のビジョンなど、個々の要素を徹底的にヒアリングし、それを反映した設計を行う。
例えば、家族が集うリビングに薪ストーブを配置したり、料理が趣味の住まい手のためにキッチンと庭をスムーズにつなぐ動線を設計したりと、生活の中での使いやすさと快適性を両立させる。今回のプロジェクトにおいては、単身赴任中の父親が家族とのコミュニケーションが減りがちとなる為、家族同士の距離感を適切に確保することが重要なポイントとなった。階段を住まいの中心に置くことで、階段が全てのエリアに接続するように構成した。これにより家族全員が必ず階段を中心にアクセスしコミュニケーションの回数が増えると藤本氏は考えた。


効率性を超えた「非効率」の価値
効率性が重視される現代において、藤本氏はあえて「非効率」と見なされるプロセスを大切にしている。例えば、図面を何度も見直し、細部に至るまで住まい手の要望に応える作業は一見効率的ではありませんが、これにより標準化された設計では得られない個性や魅力を住宅に宿らせる。このような「非効率」こそが、住まいに豊かさと深みをもたらす。
未来を見据えた住宅設計
藤本誠生建築設計事務所は、敷地、素材、住まい方という三つの要素を調和させることを通じて、自然との共生を追求しています。住宅は単なる建物ではなく、住む人々の生活と成長を支える「器」であるべきだという考え方に基づいている。
「住まいとは、ただの建物ではなく、人が暮らしと共に紡ぐ時間の器である」――この理念に基づく住宅設計は、住まい手にとっての居心地の良さだけでなく、未来の家づくりへの重要な示唆を与えてくれる存在なのかもしれない。



ナビゲーター
君島貴史(きみじま・たかし)/1975年東京生まれ。君島and株式会社 代表取締役。横浜を中心に150棟以上の建築家との住まいづくりに携わる。デザインと性能を両立した住宅を提案し続けています。「愉しくなければ家じゃない」をモットーに、住宅ディレクターとWebマガジン「andarchi」の編集を行っています。